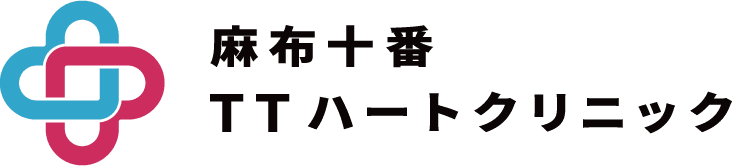早期発見から再発予防まで。
循環器と生活習慣病に特化した診療を。
麻布十番TTハートクリニックでは、「生活習慣病」と「心疾患」を中心とした保険診療に幅広く対応しています。
動悸・息切れ・胸の痛みなどの急な症状から、高血圧・糖尿病などの慢性疾患まで、正確な診断と個別最適化された治療で、患者様お一人おひとりに寄り添った医療を行っています。
心臓や血管の疾患は、早期発見と適切な管理がとても重要です。当院では、心電図・エコー・血液検査などの精密な検査機器を用い、正確な診断を行うとともに、症状や生活習慣に合わせたオーダーメイドの治療方針をご提案しています。
また、生活習慣病の管理では、食事・運動・投薬のバランスを重視し、長期的な健康維持をサポート。必要に応じて専門医療機関とも密接に連携し、患者様の「今」と「未来」を見据えた包括的な医療を実現します。



1. 生活習慣病Lifestyle-Related Diseases
1-1. 高血圧症(Hypertension)
主な症状
自覚症状が少ないが、頭痛・動悸・めまいなど
診断・治療
家庭血圧管理を含む定期的な測定と、薬物療法の段階的導入
当院の取り組み
生活指導と投薬バランスの最適化、白衣高血圧・仮面高血圧にも対応
詳しく見る | Read More
血圧が慢性的に高い状態が続く病気です。
自覚症状が少ないまま動脈硬化を進行させ、心臓病・脳卒中・腎不全の原因になります。
- 目標血圧
- 75歳未満:130/80mmHg未満
- 75歳以上:140/90mmHg未満
※合併症の有無などで個別に調整します。
1-2. 糖尿病(Diabetes)
主な症状
口渇、多尿、体重減少、疲労感
診断・治療
HbA1c・空腹時血糖などを元に、食事・運動療法、薬物療法を導入
当院の取り組み
合併症予防のための眼底検査・腎機能管理・専門医紹介体制
詳しく見る | Read More
血液中の血糖値が慢性的に高くなる病気です。
動脈硬化、心臓病、脳卒中、腎不全、視力障害など、様々な合併症を引き起こすため、適切な管理が重要です。
- 目標値
- 空腹時血糖:110mg/dL未満
- 食後2時間血糖:140mg/dL未満
- HbA1c:6.5%未満(個別に調整)
1-3. 脂質異常症(Dyslipidemia)
主な症状
基本的に無症状だが、動脈硬化進行のリスクあり
診断・治療
LDL・HDL・中性脂肪の検査、スタチン等による治療入
当院の取り組み
動脈硬化性疾患の予防を目的とした長期的管理
詳しく見る | Read More
血液中のコレステロールや中性脂肪の値が異常になる病気です。
動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。生活習慣の改善と、必要に応じて薬物治療を行います。
- 目標値
- LDLコレステロール(悪玉):
- 一般:120mg/dL未満
- 高リスク(糖尿病、冠動脈疾患既往など):70mg/dL未満
- HDLコレステロール(善玉):40mg/dL以上
- 中性脂肪:150mg/dL未満
- LDLコレステロール(悪玉):
1-4. メタボリック症候群(Metabolic Syndrome)
主な症状
腹囲増加、脂質異常、高血圧、耐糖能異常の複合症候群り
診断・治療
ウエスト測定、血液検査、生活習慣改善指導中心
当院の取り組み
生活習慣全体を見直す包括的支援プログラムを提供
詳しく見る | Read More
メタボリック症候群(Metabolic Syndrome)とは、内臓脂肪型肥満を背景に、高血圧・高血糖・脂質異常が重なった状態のことをいいます。この状態が続くと、動脈硬化が急速に進行し、心筋梗塞・脳卒中・閉塞性動脈硬化症などのリスクが大幅に高まります。
- 診断基準(日本の基準)
- 必須項目(腹囲)
- 男性:85cm以上
- 女性:90cm以上
- 以下のうち2項目以上
- 中性脂肪:150mg/dL以上 または 薬物治療中
- HDLコレステロール:40mg/dL未満 または 薬物治療中
- 血圧:収縮期130mmHg以上 または 拡張期85mmHg以上、または治療中
- 空腹時血糖:110mg/dL以上 または 治療中
- 必須項目(腹囲)
腹囲が基準以上で、さらにこの表の2項目以上に該当する場合、メタボリック症候群と診断されます。
- メタボの怖さ
見た目は元気でも、血管の内側では動脈硬化が進行し、血管が硬く狭くなる危険な状態です。
心筋梗塞・脳卒中の発症リスクは通常の3~5倍に。放っておくと命に関わることもあります。
必要に応じて、高血圧・高血糖・脂質異常の薬物治療を行います。- 治療と予防
- 内臓脂肪を減らすことが最優先
- 食事療法(減塩・低脂肪・バランスの良い食事)
- 有酸素運動(ウォーキング・軽いジョギングなどを週3〜5回)
- 禁煙
- 十分な睡眠、ストレス管理
- 以下のうち2項目以上
- 中性脂肪:150mg/dL以上 または 薬物治療中
- HDLコレステロール:40mg/dL未満 または 薬物治療中
- 血圧:収縮期130mmHg以上 または 拡張期85mmHg以上、または治療中
- 空腹時血糖:110mg/dL以上 または 治療中
- 治療と予防
- 当院の取り組み
当院では、メタボリック症候群の早期発見・改善に力を入れています。- 血液検査、血圧測定、腹囲計測
- 生活習慣指導、栄養相談
- 心血管リスク評価(動脈硬化検査・心電図・心エコー)
- 必要に応じた薬物治療
「将来の心臓病・脳卒中を防ぐため」に、今できることを一緒に取り組んでいきましょう。
1-5. 高尿酸血症(Hyperuricemia / Gout)
主な症状
足の親指の激しい痛み(痛風発作)
診断・治療
血中尿酸値の確認、尿酸降下薬の使用と食事指導
当院の取り組み
再発予防に向けた指導、腎障害・結石リスクの管理
詳しく見る | Read More
高尿酸血症(こうにょうさんけっしょう)とは、血液中の尿酸の濃度が高くなる状態をいいます。
尿酸は、体内の細胞が分解されるときにできる老廃物で、通常は尿として排泄されますが、尿酸の産生が多かったり、排泄がうまくいかないと血液中にたまってしまいます。
- 診断基準
- 血清尿酸値が7.0mg/dL以上の場合、高尿酸血症と診断されます。さらに、9.0mg/dL以上の場合は、症状がなくても積極的に治療が必要です。
- 高尿酸血症の種類
- 産生過剰型:プリン体の過剰摂取、細胞の破壊(白血病など)
- 排泄低下型:腎機能低下、アルコール、多量の果糖摂取
- 混 合 型:上記の両方
- 高尿酸血症が引き起こす病気
- 痛風
» 尿酸が関節に結晶としてたまり、突然激しい痛みを引き起こす病気 - 尿路結石
» 尿酸が腎臓・尿管で結晶化し、結石を作る - 動脈硬化、心血管疾患
» 高尿酸血症は、動脈硬化の独立したリスク因子 - 慢性腎臓病(CKD)
» 腎機能が悪化し、さらに尿酸が排泄されにくくなる悪循環
- 痛風
- 治療と予防
- 食事療法
- プリン体の多い食品を控える(レバー、魚卵、ビールなど)
- 野菜・海藻・きのこ類を多く摂る
- アルコール、とくにビール・焼酎・日本酒は控える
- 適度な運動・減量
- 水分摂取(1日1.5〜2ℓ)
- 薬物療法(尿酸を下げる薬)
- 尿酸生成抑制薬(アロプリノール、フェブキソスタットなど)
- 尿酸排泄促進薬(ベンズブロマロン、ドチヌラドなど)
- 当院の取り組み
当院では、- 血液検査による尿酸値チェック
- 生活習慣の改善指導
- 痛風発作の早期治療・再発予防
- 動脈硬化リスクの総合管理
を行い、患者さんの将来の健康を守るお手伝いをしています。
2. 心疾患Cardiovascular Diseases
2-1. 不整脈(Arrhythmia)
主な症状
動悸、胸がドキドキする、脈が飛ぶ、めまい、失神など
診断・治療
心電図・ホルター心電図・運動負荷試験・心エコーなどを用い、薬物療法や専門機関と連携したカテーテルアブレーションなどの紹介も実施
当院の取り組み
症状の再現性が乏しいケースもあるため、定期的なモニタリングと個別指導に注力
詳しく見る | Read More
心臓のリズムが乱れる病気の総称です。
動悸、息切れ、めまい、失神の原因になることもあり、放置すると命に関わることもあります。当院では以下のような不整脈を診療しています。
- 上室期外収縮
心房や房室接合部から早いタイミングで心拍が発生する不整脈。多くは良性ですが、頻度が多い場合は治療が必要です。 - 心房細動
心房が不規則に細かく震え、脈がバラバラになる不整脈。脳梗塞の原因にもなるため、適切な治療と管理が必要です。 - 心房粗動
心房が一定の速さで規則的に震える不整脈。心房細動と似た症状がありますが、治療法が異なる場合もあります。 - 発作性上室性頻拍
突然始まり突然止まる、非常に速い脈拍になる不整脈。失神の原因になることもあります。 - 心室期外収縮
心室から早いタイミングで心拍が発生する不整脈。多くは良性ですが、頻度や症状によっては治療が必要です。脈が跳ぶ感じがあります。 - 心室頻拍
心室が非常に速く収縮する危険な不整脈。放置すると心停止につながることもあり、早急な治療が必要です。 - 洞不全症候群
心臓のペースメーカー役である洞結節の働きが低下し、脈が遅くなる病気。失神や息切れの原因になります。 - 房室ブロック
心房と心室をつなぐ電気の伝わりが悪くなる病気。重症例ではペースメーカーが必要になることもあります。 - Brugada(ブルガダ)症候群
突然死のリスクがある遺伝性の疾患。心電図で典型的な波形が得られる。 - QT延長症候群
心電図でQT時間が延長し、突然死のリスクが高くなる疾患
- 当院の不整脈治療の取り組み
当院では、不整脈の専門医として5000件以上のカテーテルアブレーション実績をもとに、患者さん一人ひとりの症状とリスクに合わせた最適な治療・管理を行っています。- 診断の徹底
- 12誘導心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図を駆使し、発作性の不整脈も見逃しません
- 心エコー検査、血液検査で、心臓の構造や他疾患の影響も総合評価
- 遺伝性不整脈(ブルガダ症候群、QT延長症候群など)についても、心電図と家族歴、必要に応じ遺伝子検査を実施
- 専門的な治療
- カテーテルアブレーション
心房細動・心房粗動・発作性上室性頻拍・心室性期外収縮・心室頻拍に対して、提携病院と連携し、短期入院で安全・確実な根治治療を行います - 薬物療法
β遮断薬、抗不整脈薬、抗凝固薬を適切に選択し、副作用・再発リスクをしっかり管理 - デバイス治療
洞不全症候群、房室ブロックに対するペースメーカー治療、心室頻拍・致死性不整脈に対する植え込み型除細動器(ICD)の適応も迅速に判断し、専門施設と連携
- カテーテルアブレーション
- 再発・突然死の予防
- 不整脈の再発を防ぐ生活指導
- 適度な運動
- 飲酒・喫煙・ストレス管理
- 睡眠時無呼吸の評価・治療
- 心不全・心筋症・高血圧・糖尿病・脂質異常症などの総合管理で、不整脈の背景疾患も同時にしっかりコントロール
- 定期検査・経過観察による再発の早期発見
- 患者さんとご家族への丁寧な説明
- 図やイラストを用いて、不整脈の種類・治療法・リスクをわかりやすく説明
- 治療のタイミング、方法、費用、入院日数、生活の注意点など、患者さんが安心して治療に臨めるよう丁寧にサポート
- 遺伝性不整脈の方には、家族の方への検査・フォロー体制もご提案
- クリニックならではの強み
- 街のかかりつけ医として、突然の動悸・胸痛・めまい・失神にも迅速対応
- 専門病院と連携した万全の医療ネットワーク
- 未病・予防医学(点滴治療・血管ケア)も取り入れた包括的心臓ケア
- 診断の徹底
2-2. 心不全(Heart Failure)
主な症状
息切れ、疲れやすい、足のむくみ、夜間の呼吸困難
診断・治療
BNP検査や胸部X線、心エコーに基づく重症度評価と薬物療法の最適化
当院の取り組み
再入院予防のための生活指導、利尿薬・β遮断薬の調整、連携医療体制の整備
詳しく見る | Read More
心不全(しんふぜん)とは、「心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態」のことを言います。
病気の名前のように思われがちですが、実は「症状の集まり(症候群)」です。さまざまな心臓病や高血圧、弁膜症、不整脈、心筋症などが原因となって起こります。
- 心不全の主な症状
- 息切れ
階段を登ったり、少し動くだけで息苦しくなる。進行すると、横になると苦しくなる(起座呼吸)こともあります。 - むくみ
足や顔、腹部にむくみが出ることがあります。夜間の頻尿も特徴のひとつです。 - 疲れやすい
体を動かすとすぐ疲れる、だるさが抜けない、といった症状も心不全のサインです。
- 息切れ
- 心不全の分類
心不全は大きく急性心不全と慢性心不全に分けられます。- 急性心不全:突然発症し、呼吸困難や血圧低下など命に関わる状態。緊急治療が必要です。
- 慢性心不全:長期間かけて徐々に進行。症状と治療をコントロールしながら生活していくことが求められます。
- 心不全の原因疾患
心不全の背景には、以下のような病気が隠れています。- 虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)
- 高血圧症
- 心筋症(拡張型・肥大型など)
- 弁膜症
- 不整脈(心房細動など)
- 先天性心疾患
- 心筋炎
- 貧血や甲状腺機能異常 など
- 治療と管理
心不全の治療は、原因疾患の治療とともに- 内服薬(利尿薬、β遮断薬、ACE阻害薬、ARNIなど)
- 生活習慣の改善(減塩、体重管理、禁煙、適度な運動)
- 心臓リハビリテーション
などを行います。重症例では、カテーテル治療、ペースメーカー、心臓手術が必要になることもあります。
- 当院の心不全治療の取り組み
当院では、心不全の早期発見・再発予防・生活支援に力を入れ、患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドの治療・ケアを行っています。
心不全は「再発と入退院の繰り返し」を防ぐことがとても大切です。当院では以下の取り組みを行っています。- 早期発見・正確な診断
- 心電図、胸部レントゲン、心エコー検査で心臓の状態を的確に評価
- 血液検査(BNP、NT-proBNP)で心不全の重症度を数値で把握
- 不整脈・心筋症・虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)など心不全の原因を徹底的に診断
- 睡眠時無呼吸症候群の評価も行い、心不全悪化の隠れた要因も見逃しません
- 治療の最適化
- 薬物療法の調整
β遮断薬、ACE阻害薬、ARNI、利尿薬、SGLT2阻害薬など最新のエビデンスに基づいた薬剤を適切に組み合わせ、症状・心機能・腎機能に応じた個別最適化を行います。 - 不整脈の治療
心房細動・心室性頻拍・徐脈性不整脈の合併が心不全悪化の要因になるため、カテーテルアブレーションやペースメーカー治療も積極的に行います - 心臓リハビリの指導
安全に運動できる範囲を評価し、無理のない運動療法・日常生活のアドバイスを行います
- 薬物療法の調整
- 再発予防・生活指導
- 体重・血圧・脈拍の自己管理を指導し、悪化の早期サインを見逃さない
- 塩分・水分制限、禁酒・禁煙、適切な運動、睡眠指導を細かく指導
- ストレスケア・心のサポートも重視し、心身両面からケア
- ご家族への説明・指導も丁寧に行い、家庭での管理体制も支援
- 専門病院との連携体制
- 急性心不全やデバイス治療が必要な場合は、提携する高度医療機関へ迅速に紹介・連携
- 治療後は当院で継続的にフォローし、再発予防と生活支援を行います
- 予防医学への取り組み
- 未病の段階で心不全を防ぐ
- 高血圧、糖尿病、脂質異常症、動脈硬化、肥満の管理
- 心臓の血流や血管の状態をチェックし、再生医療・点滴療法も併用
- 心不全リスクのある方には定期健診プログラムをご用意
- 街のクリニックとして
- 「病院に行くほどじゃないけど、最近息切れする」「むくみが気になる」「動悸や疲れやすさが続く」
- そんなときも気軽に相談できる街の心臓ドクターとして、患者さんと長く寄り添っていきます。
- 早期発見・正確な診断
2-3. 虚血性心疾患(Ischemic Heart Disease)
主な症状
胸痛、胸部圧迫感、背中や左肩の放散痛
診断・治療
心電図、負荷心電図、冠動脈CTなどを活用し、内科的管理と必要に応じて専門施設への迅速な紹介
当院の取り組み
発作予防と危険因子管理に重点を置き、再発予防を重視
詳しく見る | Read More
心臓の筋肉(心筋)に酸素や栄養を送る冠動脈の血流が不足することで、胸の痛みや息苦しさを引き起こす、心筋梗塞・狭心症・微小血管狭心症・INOCAを含む病気の総称です。 血管の詰まり具合や原因によって、以下のように分類されます。
- 虚血性心疾患の主な分類
- ①狭心症
冠動脈が動脈硬化やけいれんによって狭くなることで、一時的に心筋への血流が不足し、胸の痛みや圧迫感を引き起こします。- 【症状】
- 胸の中央や左胸の痛み・圧迫感
- のどや左肩、左腕、背中への放散痛
- 動いたとき(歩行・階段昇降・重いものを持ったとき)に症状が出る
- 数分で自然に治まるのが特徴
- 【種類】
- 労作性狭心症:運動や労作時に症状が出る
- 安静時狭心症:安静にしていても突然症状が出る
- 冠攣縮性狭心症(異型狭心症):冠動脈が一過性にけいれんして血管が狭くなり発症
- 【症状】
- ②心筋梗塞
冠動脈が完全に詰まり、心筋の一部が壊死する命に関わる病気。早期の治療が生死を分けます。- 【症状】
- 強い胸の痛み(20分以上続く)
- 冷や汗、吐き気、息苦しさ
- 背中、左肩、顎への放散痛
- 高齢者や糖尿病患者では症状が軽いことも
- 【治療】
- 緊急カテーテル治療(PCI)
- 血栓溶解療法(発症から時間が短い場合)
- 薬物療法(抗血小板薬・血圧管理・コレステロール管理など)
- 重症例では冠動脈バイパス手術が必要になることも
- 【症状】
- ③微小血管狭心症
冠動脈に明らかな狭窄がないのに、心臓の微小血管(とても細い血管)の血流障害によって起こる狭心症。特に女性やストレスの多い方に多く、通常のカテーテル検査では異常が見つからないのが特徴です。- 【特徴】
- 労作時・安静時どちらでも胸の痛み
- 検査で冠動脈は正常
- 冠微小血管機能検査やアセチルコリン負荷試験で診断
- 【治療】
- 冠攣縮のコントロール
- 生活習慣の改善
- 薬物療法(カルシウム拮抗薬、硝酸薬、β遮断薬など)
- 【特徴】
- ④ INOCA(イノーカ)
虚血(Ischemia)+非閉塞性冠疾患(Non-Obstructive Coronary Arteries)=カテーテル検査で狭窄がないのに心筋虚血が存在する状態のこと。微小血管狭心症、冠攣縮性狭心症、内皮機能障害なども含まれる新しい概念です。- 【特徴】
- 胸痛があるのにカテーテルでは正常
- 微小血管の異常や冠攣縮が原因
- 心筋虚血が持続すると心不全や不整脈のリスク
- 【診断方法】
- 負荷心電図、心筋シンチグラム
- 冠動脈機能検査(冠血流予備量比・微小循環抵抗検査など)
- 【治療】
- 原因に応じた薬物療法(冠攣縮・微小血管拡張)
- 生活習慣指導、ストレス管理
- 心臓リハビリテーション
- 【特徴】
- ①狭心症
- 当院の虚血性心疾患治療の取り組み
虚血性心疾患の早期発見・再発予防・生活習慣改善に力を入れ、患者さんの生活の質(QOL)を守ることを目指しています。「胸が痛い」「締め付けられる」「息苦しい」「何となく違和感がある」…そんな症状を見逃さず、重大な心筋梗塞の発症を未然に防ぐ取り組みを行っています。- 正確な診断とリスク評価
- 12誘導心電図、運動負荷心電図、心エコー検査で、心臓の状態・虚血の有無を丁寧に評価
- 冠動脈CT、心筋シンチグラフィ、MRIなど高度な画像診断は、提携する医療機関と連携し迅速に実施
- 血液検査(心筋マーカー・動脈硬化マーカー)も組み合わせ、リスクの可視化
- 微小血管狭心症・INOCAの評価
- 通常の検査で異常が出ない胸痛も、心エコー、負荷心電図、ホルター心電図、冠攣縮負荷検査、MRIを駆使し原因を追求
- 女性に多い微小血管狭心症(冠微小循環障害)や、INOCA(虚血非閉塞性冠疾患)も丁寧に診断
- 治療の最適化
- 狭心症・心筋梗塞の治療
- 急性期は、迅速に専門病院へ連携・搬送し、カテーテル治療(PCI)や冠動脈バイパス術を実施
- 慢性期は、当院での薬物療法・生活指導・心臓リハビリを行い、再発予防
- 薬物療法
- 抗血小板薬、スタチン、β遮断薬、ACE阻害薬、Ca拮抗薬、硝酸薬などを適切に選択
- 微小血管狭心症・INOCAには、β遮断薬、Ca拮抗薬、ニコランジル、トリメタジジンなどの症状改善薬を使用
- 血管内皮機能改善・動脈硬化抑制のための再生医療・点滴療法も取り入れ、未病・再発防止を目指します
- 再発予防と生活習慣管理
- 血圧・血糖・脂質・体重の管理
- 禁煙・適度な運動・減塩食・禁酒指導
- 定期検査・フォローアップで、病状の悪化・再発兆候を早期発見
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の評価も行い、心疾患リスクを総合的に管理
- 地域密着・かかりつけ医として
- 動悸・胸の違和感・息切れ・めまいがあれば、いつでも気軽に相談
- 心筋梗塞・狭心症の既往歴のある方は、定期検査と再発予防プログラムをご用意
- 麻布十番というアクセスの良さを活かし、かかりつけ医と専門治療の橋渡し役を担います
- 予防医学の取り組み
- 動脈硬化の進行予防(血管年齢チェック)
- 再発・発症予防の点滴療法・再生医療
- メタボリック症候群・高血圧・糖尿病・脂質異常症の徹底管理
- 正確な診断とリスク評価
2-4. 心筋症(Cardiomyopathy)
主な症状
動悸、息切れ、疲労感、失神発作
診断・治療
心エコー、血液検査による分類と原因検索、β遮断薬やその他心不全薬の使用
当院の取り組み
若年者や家族歴のある患者に対しての定期検診と遺伝性疾患の可能性も視野に入れた指導
詳しく見る | Read More
心筋症とは、心臓の筋肉(心筋)に異常が起こり、心臓のポンプ機能が障害される病気の総称です。
原因不明のものも多く、遺伝が関わるタイプもあります。進行すると心不全や不整脈、突然死のリスクが高くなることもあります。
- 心筋症の主な種類
- ① 拡張型心筋症(DCM)
心臓の筋肉が薄くなり、心臓の中の空間(心腔)が拡張して、血液を送り出す力が低下する病気。- 【原因】遺伝、ウイルス感染、自己免疫など
- 【症状】動悸、息切れ、疲れやすさ、むくみ
- 【合併症】心不全、不整脈、血栓塞栓症
- ② 肥大型心筋症(HCM)
心筋が異常に肥厚し、心臓がうまく広がらず、血液を十分に取り込めなくなる病気。
※特に肥大が心室中隔(左心室と右心室の間)に強く現れる閉塞性肥大型心筋症(HOCM)は、左室流出路が狭くなるため症状が強くなります。- 【原因】多くは遺伝(常染色体優性遺伝)
- 【症状】胸痛、動悸、失神、息切れ
- 【合併症】突然死(若年者の突然死原因のひとつ)、心不全、不整脈
- ③ 拘束型心筋症(RCM)
心筋が硬くなり、心臓が拡張しにくくなって、血液を十分に取り込めなくなる病気。- 【原因】アミロイドーシス、サルコイドーシス、遺伝性疾患など
- 【症状】息切れ、浮腫、疲れやすさ
- 【合併症】心拡大は少ないが心不全症状が出やすい
- ④ 不整脈源性右室心筋症(ARVC)
右心室の筋肉が脂肪や線維組織に置き換わり、右心室の機能低下と致死性の不整脈を引き起こす病気。- 【原因】多くは遺伝
- 【症状】動悸、失神、突然死
- 【診断】 心電図・心エコー・MRI・遺伝子検査
- ⑤ 二次性心筋症
他の病気や状態によって心筋に異常が起こるもの。- 虚血性心疾患(心筋梗塞後の心筋障害)
- 高血圧性心疾患
- アルコール性心筋症
- 甲状腺疾患、薬剤性
- ① 拡張型心筋症(DCM)
- 診断方法
- 心電図・ホルター心電図
- 心エコー検査
- 心臓MRI
- 遺伝子検査
- 心筋生検(必要時)
- 治療法
病型や重症度によって異なりますが、以下の治療を組み合わせて行います。- 薬物療法
- β遮断薬、ACE阻害薬、ARB、利尿薬、抗不整脈薬など
- デバイス治療
- ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、両心室ペーシング(CRT)
- カテーテルアブレーション(不整脈合併時)
- 外科手術
- 肥大型心筋症の心筋切除術、心移植
- 当院の心筋症治療の取り組み
当院では、心筋症の正確な診断と、病態に応じたきめ細やかな管理・治療を行っています。心筋症は種類によって治療方針もリスクも異なるため、専門医による早期診断と個別最適化治療がとても重要です。- 正確な診断・分類
- 心エコー検査、心電図、ホルター心電図を用いて、心臓の壁の動き・肥大・拡大・リズム異常を詳細に評価
- 血液検査(BNP、心筋障害マーカー、遺伝子検査)による補助診断
- 必要に応じて、心臓MRI、冠動脈CT、心筋シンチグラフィを提携病院と連携して実施し、より詳しい病態把握
- 遺伝性心筋症(肥大型心筋症、拡張型心筋症、拘束型心筋症、心筋緻密化障害)のスクリーニングも行います
- 治療の最適化
- 薬物療法(β遮断薬、ACE阻害薬、ARNI、利尿薬、抗不整脈薬など、心機能・症状・不整脈リスクに応じた最適な薬剤を選択)
- 心筋症特有の不整脈(心室頻拍・心房細動・房室ブロック)の管理も専門医の立場からしっかり対応
- デバイス治療・カテーテル治療
- 致死性不整脈の予防に植え込み型除細動器(ICD)
- 房室ブロック・洞不全症候群にはペースメーカー治療
- 心房細動・頻拍性不整脈にはカテーテルアブレーション※専門病院と連携し、迅速・安全に実施
- 再生医療・点滴療法も取り入れ、心筋のコンディション維持と血管ケアをサポート
- 再発・悪化の予防
- 心不全の進行防止、動悸・失神のリスク管理
- 血圧・体重・塩分・運動の適正管理
- 不整脈・突然死のリスク評価と定期チェック
- 睡眠時無呼吸症候群の評価・治療も心筋症管理に重要なため、積極的にスクリーニング
- 丁寧な説明と生活指導
- 病気のタイプ・リスク・治療方針を、図やイラストを用いてわかりやすく説明
- 遺伝性心筋症の場合は、ご家族の検査・フォローのご提案も行います
- 心不全の再発予防、運動・食事・日常生活の注意点をきめ細かく指導
- 地域密着の安心フォロー体制
- 動悸、胸痛、息切れ、失神などの症状が出たときも、すぐに相談・受診できる環境
- 専門病院との連携により、精密検査・手術・入院治療もスムーズに対応
- 治療後もかかりつけクリニックとして継続フォロー・心のケアまで対応
- 予防医学の積極的活用
- 心筋症に合併しやすい高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・動脈硬化の管理
- 再生医療、血管ケア点滴療法による未病・再発防止プログラム
- 正確な診断・分類
2-5. 閉塞性動脈硬化症(ASO)
主な症状
歩行時の足の痛み、冷感、しびれ
診断・治療
ABI検査、エコーによる血流評価、抗血小板薬の投与と生活習慣指導
当院の取り組み
早期発見と血管イベントの予防に注力
詳しく見る | Read More
閉塞性動脈硬化症(ASO:Arteriosclerosis Obliterans)とは、主に下肢の動脈に動脈硬化が起こり、血管が狭くなったり詰まったりすることで、血流が不足し、さまざまな症状が出現する疾患です。特に高齢者や糖尿病、高血圧、高脂血症、喫煙歴のある方に多く見られます。
ASOを放置すると、血流障害が進行し、最終的には壊疽(足の組織の死)に至ることがあります。最悪の場合、足の切断が必要になるケースもあるため、早期発見・早期治療が極めて重要です。
- 主な症状
- 間欠性跛行(かんけつせいはこう)
» 歩き始めは問題ないものの、一定の距離を歩くとふくらはぎや太もも、臀部などに痛みやしびれが出現し、休むと症状が軽快するのが特徴です。 - 冷感・しびれ
» 足先の血流不足により、冷たく感じたり、しびれることがあります。 - 皮膚の変化
» 皮膚が青白くなったり、乾燥や潰瘍、ひどい場合には壊疽(えそ)を起こすこともあります。 - 安静時痛
» 病状が進行すると、安静にしていても足に強い痛みを感じるようになります。
- 間欠性跛行(かんけつせいはこう)
- 診断方法
- 問診・視診・触診:脈の触れ方や皮膚の色などを確認します。
- ABI検査(足関節上腕血圧比):手と足の血圧を比較し、血流の異常を調べます。
- 超音波検査(エコー):血管の状態や血流を可視化します。
- CT・MRI・血管造影検査:詳細な血管の状態を調べるために行うこともあります。
- 治療法
病型や重症度によって異なりますが、以下の治療を組み合わせて行います。- 生活習慣の改善
» 禁煙、食事療法、運動療法(ウォーキングなど)を行います。 - 薬物療法
» 抗血小板薬や血管拡張薬、コレステロールを下げる薬などを使用します。 - カテーテル治療(血管内治療)
» 狭くなった血管をバルーンで拡張したり、ステントを挿入する治療です。 - 外科的バイパス術
» 重度の場合、詰まった部分を迂回するように人工血管や自分の血管を使って血流を確保する手術が行われます。
- 生活習慣の改善
- 当院の取り組み
- 当院では、閉塞性動脈硬化症の早期発見と予防に力を入れております。
- ABI検査機器を導入し、簡便かつ迅速に血流異常を評価可能です。
- 生活習慣指導や薬物療法の継続的なフォローアップを行っており、再発予防にも注力しています。
- 必要に応じて、専門医療機関との連携によるカテーテル治療や外科手術のご紹介も可能です。
- 足のしびれや冷感、歩行時の痛みが気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの足を守るために、私たちが全力でサポートいたします。
診療案内
循環器内科・内科
・再生医療・予防医学
| 院長 | 前田 真吾 |
| 診療従事者 | 前田 真吾 |
診療日および診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | *○ |
| 14:00〜 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | *○ |
*午前の受付は9時から12時、午後の受付は14時から17時です。
*休診日:土曜、日曜 (月曜~金曜における祝日は診療日とします。)
*第2/第4の金曜日は非常勤医師による診療となります。